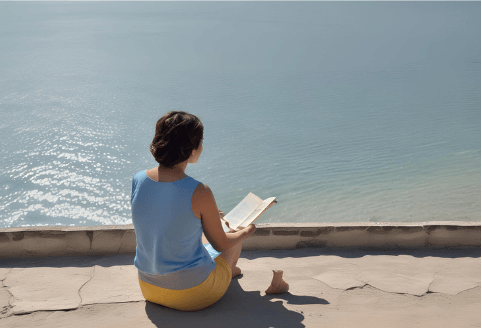ぐるぐる思考が止まらない。夜も不安で眠れない—そんな悪循環は、「考えを止める」のではなく「気づいて手放す」ことで断ち切れます。ジョセフ・グエン著『考えすぎない練習』の要点から、原因・止め方・今日からできる実践法を整理しました。
ぐるぐる思考にとらわれる理由
皆さんは、「ぐるぐる思考」にとらわれていると感じることはないでしょうか。
過去の失敗を何度も思い出したり、まだ起こってもいない誰かとの会話を頭の中で繰り返したり─「もしこう言われたら、こう返そう」と未来の場面を勝手に想像してシナリオを作っては、怒りや不安を強めてしまうのです。
人間は1日に数千から数万回もの思考をしていると言われています。研究によっては「1日6,000回」「6万回以上」など数値はまちまちですが、いずれにしても私たちが“一日中思考の洪水にさらされている”ことは確かです。そして、思考の約95%は、昨日と同じ思考パターンだと言われています。
脳は変化を嫌い同じプログラムを何度も再生し、繰り返された思考を強化し続けます。 すると、神経回路が強化され、 道ができるように整えられていきます。これが変化が難しく感じられる理由です。
毎日同じように反応し、同じ感情で生きているということになりますね。
そして、この「思考の洪水」が、ストレスや不安を増幅させ、心を疲れさせています。
そこで今回ご紹介するのが、ジョセフ・グエン氏のベストセラー『考えすぎない練習』です。本書は「思考を手放すことで心の安らぎを取り戻す」ためのヒントを、わかりやすい例えや実践法とともに教えてくれます。
思考は苦しみの根本原因
著者によれば、私たちが抱える不安やストレスの多くは「思考」から生まれます。重要なのは「考え」そのものではなく、それを際限なく追いかけ続ける「思考の量」です。
- ネガティブな感情は、頭の中で考えを巡らせ続けることで増幅する。
- 一方で、喜びや愛などポジティブな感情は「考えが少ないとき」に自然と湧いてくる。
この部分を読んで、私は強く共感しました。私自身も、何かに夢中になっているときや自然の中で過ごしているとき、頭の中の「考え」が静まり、心が自然と軽くなるのを感じます。逆に、過去の出来事や未来の不安を繰り返し考えているときほど、心は重く、動きにくくなっているものです。
つまり「どう考えるか」よりも「考え続ける量を減らす」ことが、心の軽さにつながるということですね。
そして、思考が私たちをコントロールしているとよく言われますが、思考から生まれる感情にコントロールされているのではないでしょうか。
私は長年、ヨガや瞑想を実践しています。特に瞑想では思考に気づき、コントロールする(メタ認知的活動)ことを体で学びます。
大切なのは、思考と戦うのではなく、それに気づき「手放し」「戻す」こと。
そこで、次のセクションでは、思考が湧いてくるのは自然なことと捉え、それに気づくことに注目して、著者が考える実践法をまとめてみました。
実践法 ― 思考を手放すための具体的なステップ
著者は、思考を手放し「余白」をつくることの大切さを説いています。以下に具体的な方法をまとめます。
1. 思考がネガティブ感情を生むと気づく
まず「嫌な感情の原因は自分の思考だ」と気づくことが第一歩です。
ジョセフが引用した「蛇とロープの例」では、暗がりでロープを見た人が、それを蛇だと思い込み、恐怖にかられて身動きが取れなくなります。
実際にはただのロープなのに、「蛇かもしれない」という思考が恐怖という感情を生み出しているのです。
私たちは日常でもこれと同じことをしています。
現実そのものよりも、「こうなったらどうしよう」「きっと失敗する」といった思考が、私たちの心を不安で満たしてしまうのです。
2. 考えるのをやめ、今この瞬間に戻る
過去や未来に心を置くのではなく「今」に意識を向けます。呼吸に集中したり、周囲の音や匂いを感じたりするだけで、思考が静まります。
3. 余白をつくる習慣を持つ
ジョセフ・グエン氏は本書の中で、禅の「茶碗を空にする」話を紹介しています。
知識や意見で頭がいっぱいの学者に対し、禅師が茶碗からあふれるまでお茶を注ぎ続け、「茶碗を空にしなければ何も入らない」と諭す場面です。
「茶碗がいっぱいのままでは、新しいお茶を注げない。まず茶碗(=心)を空にしなければならない。」
著者はこの逸話を通して、「私たちの心も同じだ」と伝えています。
瞑想をしたり、静かな場所で呼吸を感じたり、自然の中を歩いたり、好きな音楽を聴いたり。
─そうした「考えない時間」を意識的に持つことで、心に余白が生まれます。
頭の中が過去の記憶や未来の不安でいっぱいだと、新しいアイデアも気づきも入ってこられません。
著者は、心を空にするとは「何も考えない努力」ではなく、“考えに気づいて手放すこと”だと述べています。 その繰り返しが、心に余白をつくる練習になるということですね。
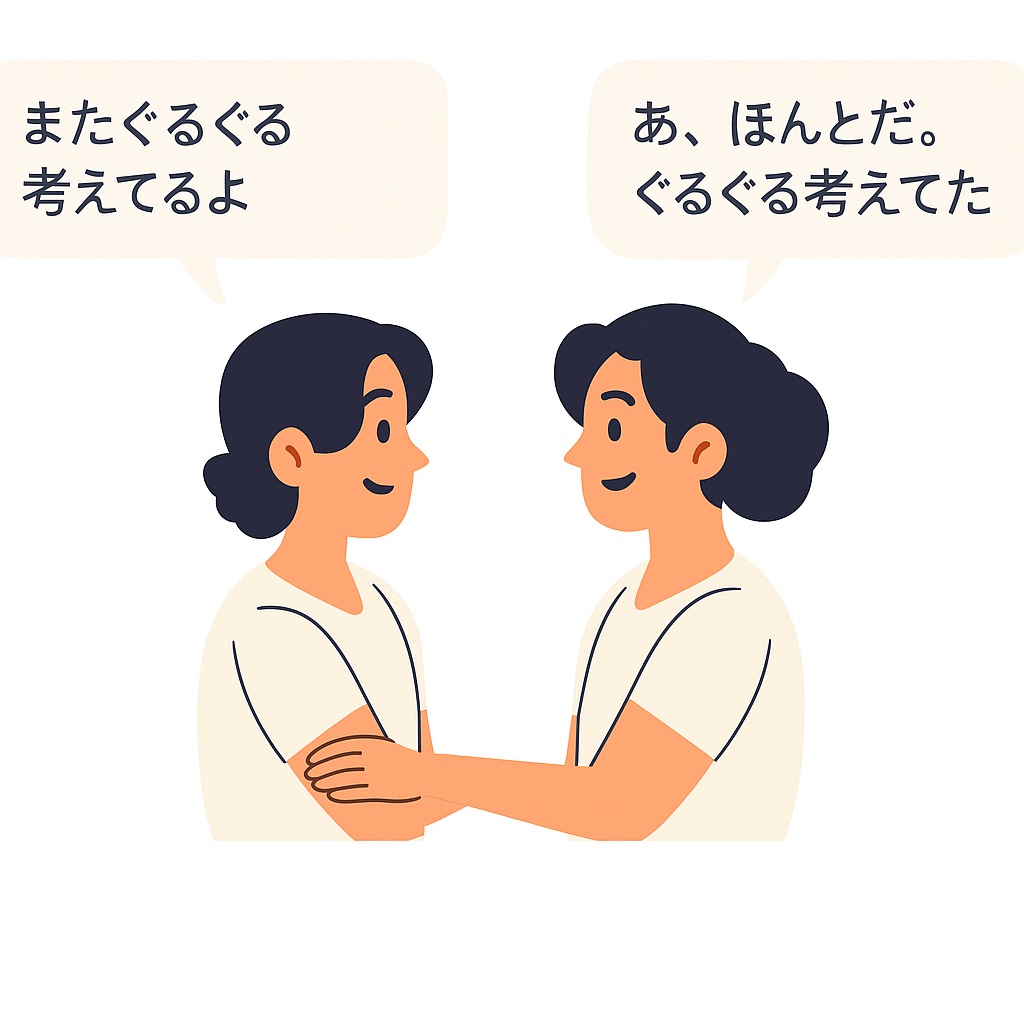
ー思考に気づき手放すこと。これはメタ認知という概念を知ることが助けになります。メタ認知については別のブログで詳しく解説する予定ですが、自分の認知を一段高いところから観察すること、認知を認知することです。
自分の中にもう一人の自分がいて、「またぐるぐる思考してるよ」「あ、ほんとだ、ぐるぐるしてる」と頭の中で会話をしているイメージですね。
思考を止めようとするのではなく、「今、考えているな」と気づいて手放す─この姿勢こそが静けさを取り戻す第一歩だと感じます。日常の中でも、この「気づき→手放す」を繰り返すことで、少しずつ心のスペース=余白が広がっていくでしょう。
4. 思考が戻っても責めない
「また考えてしまった」と自分を責める必要はありません。思考が湧いてくるのは、人間として自然なことです。大切なのは、考えてしまうことを止めることではなく、「今、思考にとらわれているな」と気づくことです。
ジョセフ・グエン氏は、「考えをやめようとすること自体が、また一つの思考になってしまう」と指摘しています。だからこそ、思考が戻ってきた瞬間に気づいたら、それをただ“やさしく見送る”だけでいいのです。
それはまるで、空に浮かぶ雲を眺めているような感覚。雲(思考)は自然に現れ、やがて風に流されていきます。無理に追い払う必要も、掴もうとする必要もありません。あなたがただ観察者でいれば、雲は自ずと過ぎ去っていきます。
この「気づいて手放す」という行為を繰り返すうちに、思考にとらわれる時間は少しずつ短くなり、心に静けさが広がっていきます。そうして生まれる“余白”の中で、─直感やインスピレーション─が聴こえるようになるのです。
責めるのではなく、気づいて、受け入れて、手放す。 その優しい循環が、思考から自由になる第一歩です。
『考えすぎない練習』が伝える “思考を手放した先にある世界”
「人生の奇跡は、考えているときではなく、“考えていないとき”に起こる。」
著者のジョセフ・グエン氏は、本書の終盤で「奇跡が起こるための余白をつくる」ことの重要性を語っています。思考を手放し、頭の中にスペースを作ることで、私たちは、宇宙や無限の知性─つまり“直感”とつながることができるのだと説いています。
考えがいっぱいに詰まった状態では、新しいアイデアも気づきも入ってこられません。逆に、心が静まり「何もしていない時間」を持つことで、まるで空の茶碗に新しいお茶が注がれるように、ひらめきや導きが自然に流れ込んでくるのです。
グエン氏は、発明王エジソンやアインシュタインもこの「余白の力」を理解していたと紹介しています。
エジソンは、難題に行き詰まると、鉄球を持ってうたた寝をし、眠りに落ちる瞬間にふと浮かぶアイデアをつかんだと言います。アインシュタインもまた、問題に直面したとき、あえて思考を中断しバイオリンを弾いて直感の声を待ったそうです。
このように、偉人たちが実践してきた「考えない時間」こそが、人生の転機を生み出すインスピレーションに出会うための「余白」になるということですね。
無の時間がインスピレーションを呼ぶ
ジョセフは、「不老(flow)状態」や「無思考の時間」を重視しています。この状態にあるとき、人は無限の知性とつながり、直感が自然に働くといいます。
アインシュタインがバイオリンを弾いているとき、エジソンがうたた寝しているとき─その静けさの中から、偉大な発想が生まれたように
私たちの人生でも、
- ふとした瞬間に良い考えが浮かぶ
- 迷っていたことに自然と答えが出る
そんな体験があるはずです。これが、思考の外側からやってくる直感=インスピレーションですね。
【補足】直感に従う勇気
私がこの本で最も心に残ったのは、著者が語るこの部分でした。
「完璧に理解してから動くのではなく、静かに受け取り、やってみる。行動することで、道は自然と見えてくる。」
著者は「思考を超えた直感に従うことで、人生が自然な流れに戻る」と説いています。
直感に従うというのは、“考えずに衝動で動くこと”ではありません。むしろ、思考を鎮めて、心の奥から聞こえる声に従うこと。
それは理屈ではなく、「なぜかそうした方がいい気がする」という感覚。その感覚を信じて行動すると、不思議と物事が流れ始めるでしょう。
無の時間を支える「瞑想」という習慣
著者は「思考を止める」方法として、瞑想をすすめています。瞑想は単なるリラックス法ではなく、脳と心を静かに整えるための“余白づくり”の時間です。
「私たちは考えることで解決するのではなく、考えないことで“見えてくる”。」
私自身も長年ヨガや瞑想を続けています。瞑想中に思考が浮かんでも、それを無理に排除せず、「あ、今考えているな」と気づいて手放す。この“気づき→手放し→戻す”という流れは、まさにメタ認知の力だと思います。
そうして心を静めたとき、ほんの一瞬ですが、何か大きなものとつながるような瞬間が訪れます。その感覚こそが、著者の言う「無思考」=インスピレーションの源なのだと書籍を通して実感することができました。
まとめ ― 思考を手放すことで見えてくる世界
『考えすぎない練習』が伝えるのは、
「考えを減らすことで、心の静けさと創造性が戻ってくる」
という、シンプルでありながら深い真理です。
そして、「考えないことは怠けることではない」ということ。むしろ、考えないからこそ、直感・インスピレーション・導きといった“奇跡”が入ってくる。グエン氏は「奇跡の大きさではなく、奇跡が入る余白の広さが大切だ」と述べています。
思考を止めようとするのではなく、気づいて、戻す。手放して、空にする。その繰り返しが余白を生みます。
私たちは、その余白に直感が降りてくるのを信じて待つ。そして、直感を心静かに受け取り自分を信じて行動する。
ジョセフ氏の教えから学び実践することで、このブログを読んでくださった方が,ぐるぐる思考から解放され、新しい世界観を創造することができますように。。
次回予告
記事を読んでくださった方の中には、「理屈では分かっていてもやっぱりぐるぐる思考になってしまう」という意見があるでしょう。
そこで次の記事では、ジョセフ氏がすすめている「無の時間」を支える瞑想と脳の関係を、科学的な視点(神経可塑性・脳波・ストレス耐性など)から掘り下げていきます。思考を減らすだけでなく、脳を整える“瞑想”を一緒に見ていきましょう。
科学的な側面から脳の仕組みを知ることが、ぐるぐる思考を理解する一助になることを願って。。。